第22回(奥村先生)ネゴシエーション研究フォーラムを開催いたしました。
2025年9月22日(月)、品川区の文化コミュニティ施設「きゅりあん」にて、第22回ネゴシエーション研究フォーラムを開催いたしました。

今回は、日本交渉協会の名誉理事でもある奥村哲史先生が8月27日に出版された『マネジメントテキスト 交渉戦略』の記念セミナーとして、「藤田先生が礎を築いた日本の交渉学―私たちが継承し展開するー」と題してお話しいただきました。
奥村先生には、かつてハーバード大学PON(Program on Negotiation)のアラン・ランプルゥ先生、オックスフォード大学PONのミシェル・ペカー先生の講演や2日に間にわたる「交渉戦略研究」講座などで大変お世話になりました。
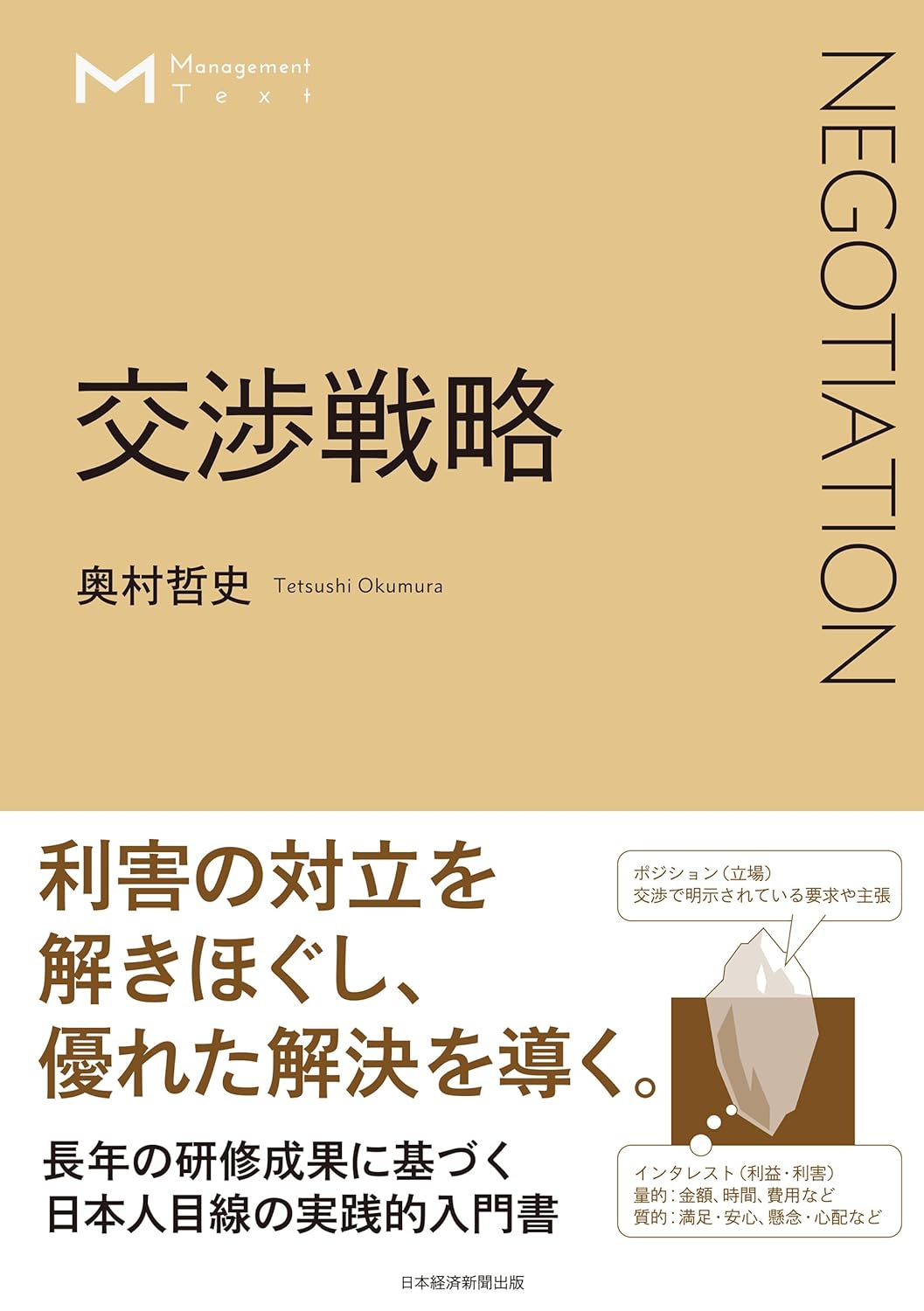
『マネジメントテキスト 交渉戦略』
日経BP 日本経済新聞出版 2025
お話の中で、ハーバード大学において世界初の交渉学講義を学ばれ、日本に交渉学を紹介した、日本交渉協会創設者でもある藤田忠先生と奥村先生との出会いから始まり、藤田先生が日本に定着させようと努力された交渉学という新しい分野に取り組まれ、経営大学院や企業研修で実務家に教えてこられた40年にわたるご経験の中から、「実践に活かせる交渉学」を目指して今回の出版に至った経緯が語られました。実際に同書はそうした経緯を踏まえて構成されていることが分かりますし、日本人に交渉学の必要を感じ、その普及に尽力された藤田先生の志のまさに「継承と展開」に相当するものだと思います。
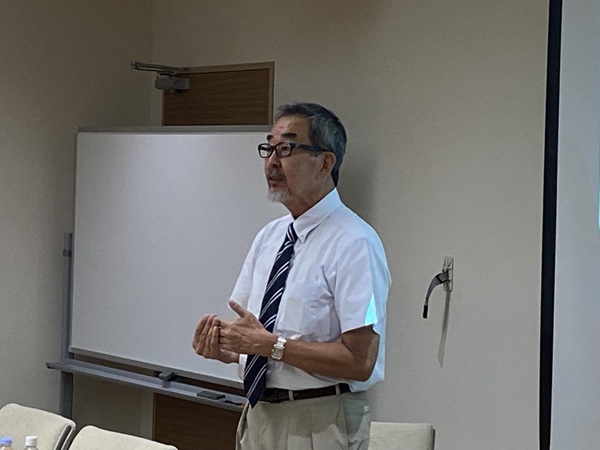
アメリカにおいては、1950年代から現実の社会問題解決のための、人文科学、経済学、心理学などによる学際研究の取り組みが始まりましたが、各学問分野の融合には難しい現実もありました。交渉の分野においては、1970年代後半に政治学、ゲーム理論、心理学などの立場から交渉研究を集合する学際コンソーシアム、PON(上述)が発足ました。
前述の通り、藤田先生は帰国後、日本における交渉研究者の育成、学問分野として確立をめざします。奥村先生も修士論文執筆時、藤田先生との出会いと当時取り組んでいた経営組織論やリーダーシップ論を追求する中で、交渉に関連する研究を進めました。
こうした日本において交渉学がたどった歩みを踏まえると、今回、経営学のテキストとして各領域の日本の第一人者が執筆する日本経済新聞出版の「マネジメントテキスト」シリーズに「交渉」が仲間入りしたことは、交渉学普及の大きな前進と言えるでしょう。
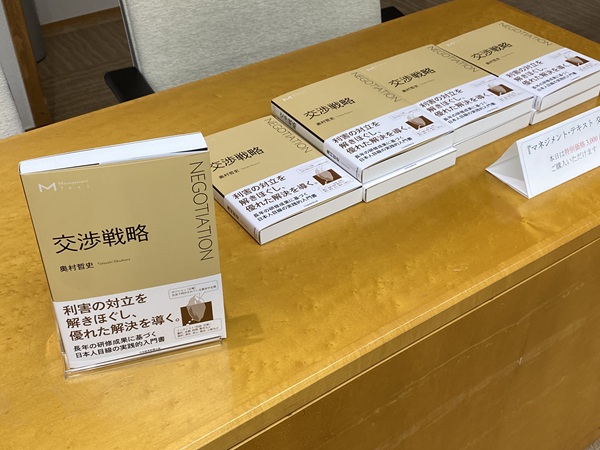
さて、交渉研究の祖ともいえる、メアリー・パーカー・フォレットの言葉を借りれば、交渉とは「『相違』の解決」のことだと言えます。相違の解決は社会生活のいたるところに存在し、私たちは意識するか否かにかかわらず、日常的に何らかの交渉を行っています。交渉は何も営業や購買に限定されるものではなく、社内外のあらゆる場面、親子関係や日常会話にも見られる普遍的行為です。しかしながら、日本に限ったことではありませんが、そのスキルが学校教育で教えられることはほとんどありません。
奥村先生の『交渉戦略』の「はじめに」に書かれているように、私たちが学校で教わる前に母国語を身に着けているようなものです。しかし、母国語の場合、ある程度習得してから後、学校教育で改めて教わります。日本で言えば、国語に始まり、その後国文法、古文、漢文というようにです。自然に身に着いている母国語を改めて文法や用法を学び改善していくのは、その言葉を体系的に理解し、文化・論理・社会的に活用できるようにするためです。その方が、社会生活での精確なコミュニケーション力、文化的教養、論理的思考力、異文化理解力などを養う点で有利だからです。一方、交渉は自然と身に着けたまま放置というのが実態です。しかし、交渉も母国語と同様、理論的に鍛え直すことで精度を増すことができます。
したがって、交渉教育においては理論を学ぶだけでなく、ケーススタディやロールプレイなどを通じた体験型も多く取り入れられています。しかしながら、書籍ではこの体験型を盛り込むことが難しい。そこで本書では事例を多く取り入れることでその欠点を補っています。中でも、「失敗」は成功体験以上に得られる知見が多い。そのため、本書では失敗事例も数多く取り入れられています。
次に、組織設計と現実とのギャップについて。ウェーバーの官僚制モデルや古典的経営学は合理的に設計された組織像を描きましたが、実際には境界の曖昧さ、非公式な影響力、文化的抵抗など多くの矛盾が存在します。その隙間を埋めるのが交渉力であり、マネジャーに不可欠な要素となります。
「ドラマは交渉からできている」
これは藤田先生がある脚本家から聞いた言葉だそうですが、例えば病院を舞台にしたドラマでは、医師と看護師の相違、事務方との相違、患者との相違、病院組織の上下関係の相違などが描かれます。しかし、これらの「相違」を解決する技術(交渉)を彼らはほとんど教わっていません。昨今では、医師に求められる必須のスキルとして共感力が重視されているようですが、病院経営の悪化に伴い、医師が忙しすぎるといった問題もあるようです。とはいえ、放置すれば紛争はエスカレートしてしまいます。
最後に、認知心理学の影響について。ゲーム理論や決定論において研究されることの多かった初期の交渉学は、1960年代、70年代ごろから社会心理学の影響を受け、80年代から90年代には認知心理学、そして90年代からは文化心理学と、心理学の見地からの研究が盛んになってきました。それにより、交渉学はより実用的なものになったということができます。奥村先生も、1997年にマックス H.ベイザーマン 、 マーガレット A.ニールの“Negotiating Rationally”を翻訳されています(『マネジャーのための交渉の認知心理学: 戦略的思考の処方箋』)。
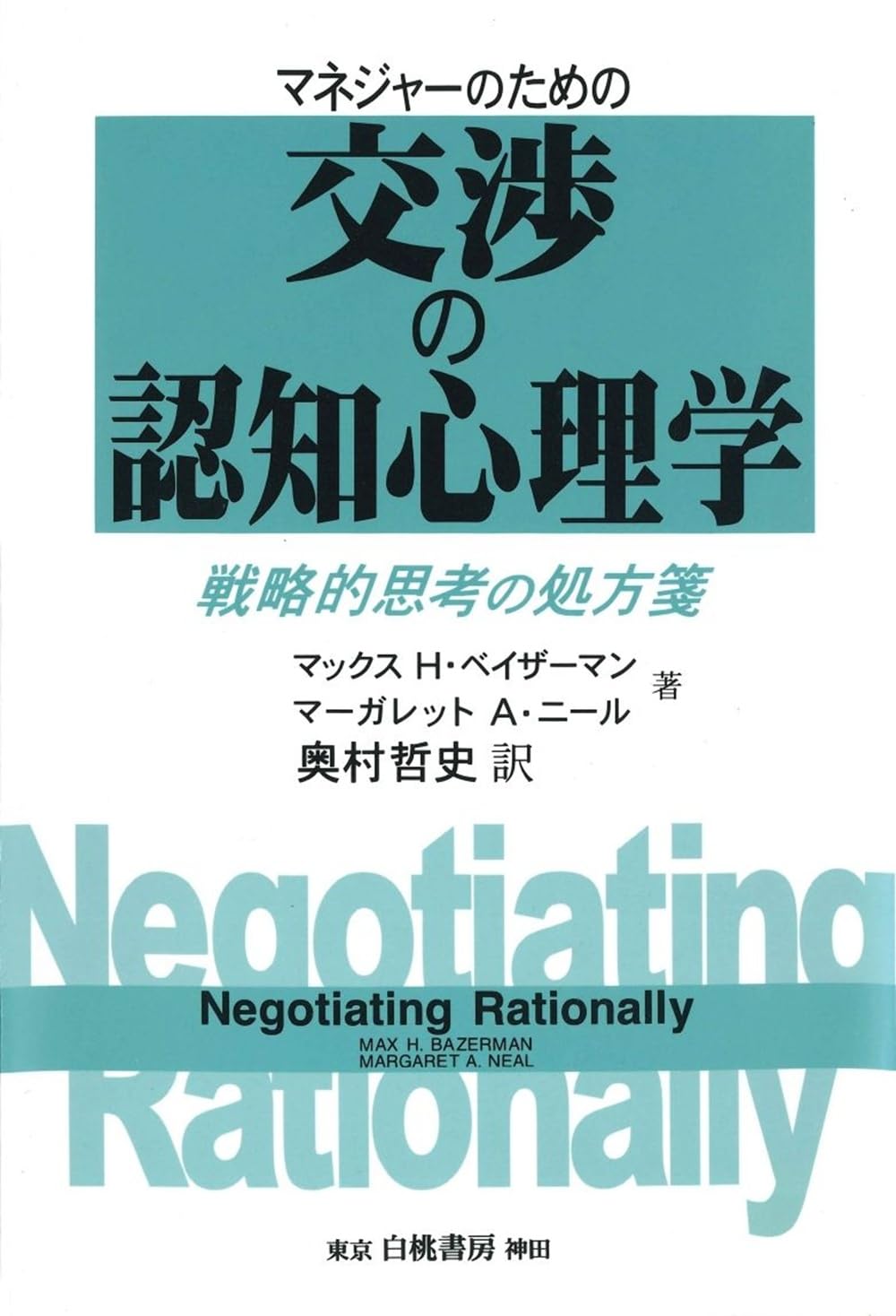
『マネジャーのための交渉の認知心理学』
白桃書房 1997
交渉は特別な人だけが行うものではなく、誰もが日常的に行っている営みです。その力を磨くことは、個人の成長のみならず、組織や社会全体の発展にも寄与します。『マネジメントテキスト 交渉戦略』は、その学びの道標となるものであり、先生は多様な交渉の場面で活用してほしいと結ばれました。
【講演者】奥村哲史 氏 プロフィール

<プロフィール>
特定非営利活動法人 日本交渉協会 名誉理事
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程修了
博士(商学:早稲田大学)
滋賀大学経済学部教授から名古屋市立大学大学院経済学研究科、東京理科大学を経て、東洋大学教授を2025年3月定年退職。
大学では経営学、経営組織論を担当し、米ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院フェロー(1994~2018)として交渉と紛争解決研究に従事。早稲田大学大学院政治学研究科(2003~2019)、神戸大学大学院経営管理研究科(2010~2019)の他、豪メルボルン大学経営大学院、仏フランスESSEC経営大学院、テンプル大学日本校企業教育部門、西セビリア大学大学院、独レーゲンスブルク工科大学、仏ストラスブール大学などで交渉関連科目を担当。企業における実務研修多数。
<翻訳>
『交渉のメソッド:リーダーのコア・スキル』
(Lempereur & Colson, The First Move 白桃書房 2014)
『予測できた危機をなぜ防げなかったのか? 組織・リーダーが克服すべき3つの障壁』
(Bazerman & Watkins, Predictable Surprises 東洋経済新報社 2011)
『影響力のマネジメント:リーダーのための実行の科学』
(Pfeffer, Managing with Power 東洋経済新報社 2008)
『交渉力のプロフェッショナル:MBAで教える理論と実践』
(Brett, Managing Globally ダイヤモンド社 2003)
『「話し合い」の技術:交渉と紛争解決のデザイン』
(Ury, Brett, & Goldberg, Getting Disputes Resolved 白桃書房2002)
『マネジャーのための交渉の認知心理学:戦略的思考の処方箋』
(Bazerman & Neale 白桃書房 1997)
『マネジャーの仕事』
(Mintzberg, The Nature of Managerial Work 白桃書房 1994)



