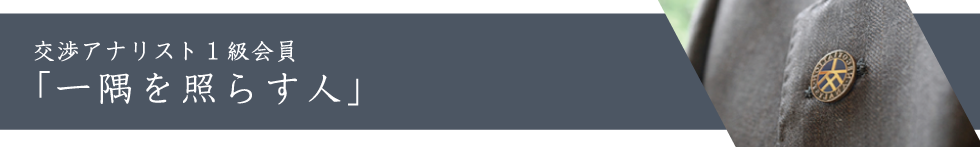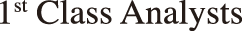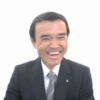交渉アナリスト1級会員
吉原 克
交渉アナリスト1級会員
吉原 克
現在のお仕事についてお聞かせください
大学卒業後、新卒で旧政府系金融機関にシステムエンジニアとして入社し、大規模な金融トレーディングシステムの開発に従事しました。その後は事業会社へ転職し、Webシステム開発からコンテンツ企画制作、Webマーケティングまで事業全般の運営に関わるIT関連業務を経験。独立してキャリアコンサルティング会社を設立してからは、ITとメディア制作を軸にエンジニアやクリエイターのキャリア支援に力を入れています。
ここ数年は後進の育成に少しでも貢献できればと、新人ITエンジニア養成研修や生成AI講座の講師としても活動しています。
ここ数年は後進の育成に少しでも貢献できればと、新人ITエンジニア養成研修や生成AI講座の講師としても活動しています。
交渉学を学ばれたきっかけ(交渉学を学ばれる前に苦労された経験など)
会社員時代は一貫してIT技術職やクリエイティブ職に従事しており、営業経験はゼロ。全員エンジニア職だった新卒の会社ではそれで問題なかったのですが、転職した先はバリバリの営業会社で営業の言うことは絶対。システムやコンテンツを作る側としては、無理な条件で案件を獲得してくる営業に対して主張する権限も交渉能力も持ち合わせておらず、ひたすら徹夜で無理を通すしかありませんでした。
その後は独立し、マイクロ法人の社長として“実質、営業”として案件をまとめる立場になったものの、営業の交渉経験不足で毎回しどろもどろ。何かしら拠り所となる方法論を習得する必要性を感じていました。そんな折、早稲田NEOの講座告知で目にした「交渉アナリスト2級講座」。モノは試しと申し込んでみたらこれが大正解!分配型でなく統合型の交渉があると知り、私が求めていたものはこれだ!と迷わず駆け足でその年のうちに1級まで取得しました。
その後は独立し、マイクロ法人の社長として“実質、営業”として案件をまとめる立場になったものの、営業の交渉経験不足で毎回しどろもどろ。何かしら拠り所となる方法論を習得する必要性を感じていました。そんな折、早稲田NEOの講座告知で目にした「交渉アナリスト2級講座」。モノは試しと申し込んでみたらこれが大正解!分配型でなく統合型の交渉があると知り、私が求めていたものはこれだ!と迷わず駆け足でその年のうちに1級まで取得しました。
交渉学を学んでどう実践していますか?
交渉学を学んでから、仕事でも私生活でも、ただの「勝ち負け」ではない対話の可能性を強く意識するようになりました。
ビジネスの営業交渉では、特にZOPA(交渉可能領域)を想定してのアンカリングを活用することで、有利な条件で話を進めやすくなりました。現状、交渉学を理解している相手はほとんどおらず、いわば「免疫がない」状態。そのため、交渉の基本を押さえているだけで効果は絶大。「時代の先行者利益」を得ていると実感しています。
一方、私生活では何気ない雑談の中から、相手自身も気づいていない本当のニーズを見抜く力がつきました。例えば、常に毒舌で人の揚げ足を取る人が、実は「頭の良さを認めてほしい」劣等感の塊だったりすることに気づく。交渉学のメソッドで発言や態度を因数分解することで、まるで心理学を学んだかのように人の本音が見えてくるのです。
こうした経験を積むうちに、人間全体として以前よりも懐が深くなり、それでいて妥協せずに自分の要望を通せる有能さを得られたのではないかと感じています。
ビジネスの営業交渉では、特にZOPA(交渉可能領域)を想定してのアンカリングを活用することで、有利な条件で話を進めやすくなりました。現状、交渉学を理解している相手はほとんどおらず、いわば「免疫がない」状態。そのため、交渉の基本を押さえているだけで効果は絶大。「時代の先行者利益」を得ていると実感しています。
一方、私生活では何気ない雑談の中から、相手自身も気づいていない本当のニーズを見抜く力がつきました。例えば、常に毒舌で人の揚げ足を取る人が、実は「頭の良さを認めてほしい」劣等感の塊だったりすることに気づく。交渉学のメソッドで発言や態度を因数分解することで、まるで心理学を学んだかのように人の本音が見えてくるのです。
こうした経験を積むうちに、人間全体として以前よりも懐が深くなり、それでいて妥協せずに自分の要望を通せる有能さを得られたのではないかと感じています。
交渉学を今後どのように活かしていきますか(交渉に対する姿勢、モットーなど)
交渉学を学ぶことで、単なるビジネスの枠を超え、地域社会や家庭生活、友人関係といった様々な局面で、人々がより良い意思決定ができる知性を広めていきたいと考えています。というのも現在の社会には「勝ち負け」だけで物事を判断し、勝てば官軍、負ければ全てを失うといった古い価値観がまだ根強く残っています。だからこそ必死で勝とうと他人を蹴落とすことも厭わない姿勢があたかも正解であるかのように持て囃されがち。その結果、不必要に追い詰められ泣きを見る人が生まれるうえに、そうした人がいる分だけ全体として得られる成果もすり減ってしまう結果になりつつ「世の中そんなもんだよ」とみんながモヤモヤを抱えたまま……。そんな残念な有様を少しでもアップデートしていきたいという思いがあります。もちろん、スポーツの試合のように勝者と敗者が生まれる局面があることは否定しません。勝つことで得られるもの、負けることで感じる悔しさや喪失感も、そうしたルールの場をあえて選んで経験するからには人間の成長に寄与する部分は大きいと思ってはいます。ただそれでも、社会を見渡せば「交渉学を知っている人がいれば、もっと良い解決策に辿り着けるはずなのに」と歯痒く思う状況の方が圧倒的に多いと感じています。
私自身、まだ学びの途中ではありますが、交渉学という「叡智」を広めることで、本来ならば悲しまずに済むはずの人たちが本当に泣きを見ることなく、より良い未来を選び取れるよう貢献していきたいです。
私自身、まだ学びの途中ではありますが、交渉学という「叡智」を広めることで、本来ならば悲しまずに済むはずの人たちが本当に泣きを見ることなく、より良い未来を選び取れるよう貢献していきたいです。