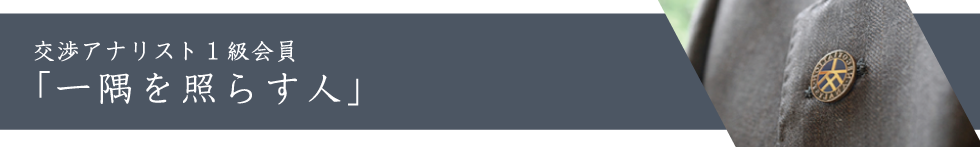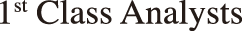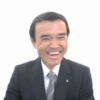交渉アナリスト1級会員
吉山 洋一
交渉アナリスト1級会員
吉山 洋一
これまでのお仕事の経歴についてお聞かせください
CADエンジニア、遠隔会議ソリューションの企画・導入、レンタルサーバ会社の立ち上げ、医療ITクラーク、民間企業および公的機関のITプロジェクトなど、多岐にわたるプロジェクトに携わってまいりました。技術分野に留まらず、マネジメントやビジネスの視点を活かし、プロジェクトの企画、推進、実践に取り組んできました。
また、本業と並行して、家電量販店でのパソコン販売、コールセンターでのSV業務やクレーム対応、居酒屋での接客など、多様な現場で対人コミュニケーションや交渉を実践から学びました。
現在は、株式会社国際協力データサービスにおいて、DX推進、セキュリティコンサルティング、新規事業開発、人財教育を軸に活動しています。2016年より流通経済大学の客員講師としてプロジェクトマネジメントの講義を担当し、後進の育成に取り組んでいます。
また、本業と並行して、家電量販店でのパソコン販売、コールセンターでのSV業務やクレーム対応、居酒屋での接客など、多様な現場で対人コミュニケーションや交渉を実践から学びました。
現在は、株式会社国際協力データサービスにおいて、DX推進、セキュリティコンサルティング、新規事業開発、人財教育を軸に活動しています。2016年より流通経済大学の客員講師としてプロジェクトマネジメントの講義を担当し、後進の育成に取り組んでいます。
交渉学を学ばれたきっかけ(交渉学を学ばれる前に苦労された経験など)
かつての私は、「正しさを証明し、相手を威圧して圧倒すれば交渉は成立する」と考えていました。実際、過去に所属していた組織で、社会的に権威のある方から「人を動かすのは、金と権力と恐怖だ」と叩き込まれ、その考えを無意識に信じていました。今、振り返れば未熟だったと笑えますが、当時は本気で信じて実践していました。しかし、その驕りを打ち砕く交渉の場面がいくつも訪れました。なかでも、足掛け5年にわたる遺産相続問題は大変でした。ある日、40年以上も放置されていた土地について、親戚を名乗る人物から突然、相続権を主張する手紙が届きました。相続人は私を含め4人。そのうちの1人は、過去にその手紙の主から土地を騙し取られた経験があると聞かされました。また、私の母も過去に脅されたことがあると聞かされ、今回も同じ手口で騙されるのではないかという不安がよぎりました。その不安は的中し、交渉は疑心暗鬼の中で暗礁に乗り上げました。その後、先方は弁護士をたてて交渉に臨み、私もその弁護士や親戚と話し合いを重ねながら、少しずつ解決へ向けて進めていきました。最終的には、全員が譲歩する形で合意に至りましたが、家族を巻き込んだ苦い経験として今も心に残っています。
こうした経験を通じて、「騙される人を少しでも減らしたい」という想いと、「自分自身の交渉スタイルを見直したい」という気持ちが芽生え、交渉アナリスト養成講座に参加。そこで、自分が井の中の蛙だったことを痛感し、本格的に交渉学を学ぶようになりました。
こうした経験を通じて、「騙される人を少しでも減らしたい」という想いと、「自分自身の交渉スタイルを見直したい」という気持ちが芽生え、交渉アナリスト養成講座に参加。そこで、自分が井の中の蛙だったことを痛感し、本格的に交渉学を学ぶようになりました。
交渉学を今後どのように活かしていきますか(交渉に対する姿勢、モットーなど)
交渉学を学ぶことで、交渉を「利害の対立を解決する手段」ではなく、「ステークホルダー間で信頼関係を築き、価値を創造するプロセス」と捉えるようになりました。もともと、「交渉で騙される人を減らしたい」「周囲の良い人たちの交渉力を高めたい」という想いがありました。しかし、それだけではなく、交渉は単なる対立の解決ではなく、より有意義で価値を生み出すプロセスになると考えるようになりました。
現在は、プロジェクトの合意形成、企業の意思決定支援、人財育成などに交渉学を活かし、実践を重ねています。特に、IT・セキュリティ・DX推進の分野では、認知的アプローチを取り入れた戦略的意思決定の実践と支援に努めています。
交渉は、単なる技術ではなく、「関係性をデザインし、価値を共創するプロセス」であり、常に学び続ける学問であると考えています。
今後も実践と研究を深め、交渉による、より良い意思決定の実践と支援を続けていきます。
現在は、プロジェクトの合意形成、企業の意思決定支援、人財育成などに交渉学を活かし、実践を重ねています。特に、IT・セキュリティ・DX推進の分野では、認知的アプローチを取り入れた戦略的意思決定の実践と支援に努めています。
交渉は、単なる技術ではなく、「関係性をデザインし、価値を共創するプロセス」であり、常に学び続ける学問であると考えています。
今後も実践と研究を深め、交渉による、より良い意思決定の実践と支援を続けていきます。