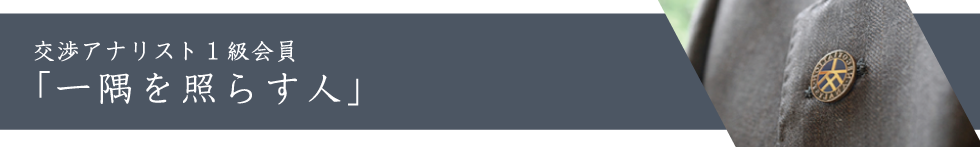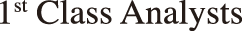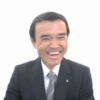交渉アナリスト1級会員
高橋 道生
交渉アナリスト1級会員
高橋 道生
これまでのお仕事の経歴についてお聞かせください
地元に海外から訪れる旅行客や視察団の「英語通訳兼ガイド」として、活動の幅を広げているところです。
交渉学を学ばれたきっかけ(交渉学を学ばれる前に苦労された経験など)
交渉学は、仕事での商談はもちろん、社内の調整や家庭での話し合いにも応用できると考え、学び始めました。
若い頃アメリカに住んでいた時は「言わなければ伝わらない」という意識が強く、つい強引に自己主張してしまうことが多々ありました。逆に日本に戻ってからは「場の空気を壊さないこと」を優先しすぎて、発言を控えてしまう場面もあります。
「上手な自己主張」の方法を探していた時に、日本交渉協会に出会ったのが大きなきっかけです。
若い頃アメリカに住んでいた時は「言わなければ伝わらない」という意識が強く、つい強引に自己主張してしまうことが多々ありました。逆に日本に戻ってからは「場の空気を壊さないこと」を優先しすぎて、発言を控えてしまう場面もあります。
「上手な自己主張」の方法を探していた時に、日本交渉協会に出会ったのが大きなきっかけです。
交渉学を学ばれて現場でどう実践されていますか(統合型交渉の実践の例など)
安易に分配型交渉に入るのではなく、常に統合型交渉ができないか考えるようにしています。交渉後も良好な関係を続けることが大事なのですから、奪い合いや片方だけが満足するような結果を招かないように気をつけています。交渉学の理論を学んだことで、冷静に、そして自信を持って交渉のシナリオを描けるようになりました。
交渉学を今後どのように活かしていきますか(交渉に対する姿勢、モットーなど)
最も大切にしたいことは、交渉後に合意した証として気持ちよく握手ができることです。
統合型交渉をするには、交渉相手のことを事前によく知ることが必要です。相手のこととは、社会的立場や交渉の常套手段というのもありますが、交渉することになった本当の理由と、最終的にどのような結果を希望しているのかということです。相手側の交渉担当者の社内的立場や権限、交渉事項の譲歩範囲も事前に把握できれば、こちら側は交渉カード(選択肢)を多く準備しておくことができます。交渉を有利に、そして心情的にも余裕を持った交渉、究極は相手にとっても魅力的な提案ができるような交渉をしていきたいと考えております。
統合型交渉をするには、交渉相手のことを事前によく知ることが必要です。相手のこととは、社会的立場や交渉の常套手段というのもありますが、交渉することになった本当の理由と、最終的にどのような結果を希望しているのかということです。相手側の交渉担当者の社内的立場や権限、交渉事項の譲歩範囲も事前に把握できれば、こちら側は交渉カード(選択肢)を多く準備しておくことができます。交渉を有利に、そして心情的にも余裕を持った交渉、究極は相手にとっても魅力的な提案ができるような交渉をしていきたいと考えております。